- HOME
- 探す・調べる
- 図書館を使う
- 学習・教育
- 研究支援
- 図書館について
第3章 北里柴三郎
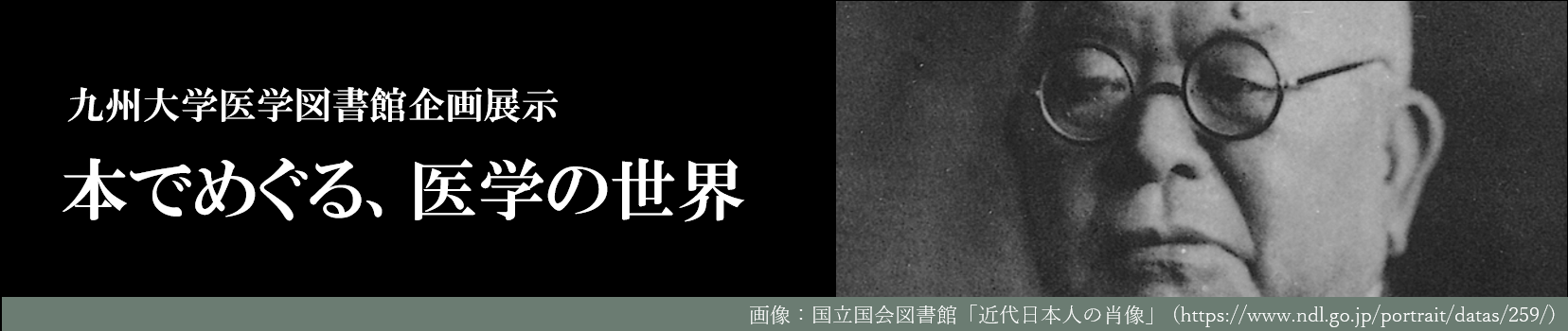
北里柴三郎(きたざと しばさぶろう / 1853–1931)
感染症に挑み続けた、近代日本医学の父
北里柴三郎は、日本における近代医学・細菌学の礎を築いた医師・細菌学者です。
熊本の阿蘇郡小国郷北里村に生まれた柴三郎は、東京医学校(現・東京大学医学部)で学んだ後、ドイツに留学し、細菌学の祖ロベルト・コッホのもとで研究を行いました。
1889年には破傷風菌の純粋培養に世界で初めて成功し、翌年にはその抗毒素(毒素に対抗する免疫物質)を発見。これにより感染症に対する血清療法の基礎が築かれました。
1892年に帰国し、伝染病研究所を設立。
1894年、香港でのペスト大流行に対処するため現地入りし、短期間で病原菌(ペスト菌)を発見。のちにアレクサンダー・イェルサンとともに、その発見は国際的に認められています。
1914年、伝染病研究所が文部省に移管されるのに反対して辞職し、あらたに北里研究所を設立。日本における感染症研究や医学教育の発展に尽力し、特に臨床と基礎医学をつなぐ研究体制の確立を重視し、後進の育成にも力を注ぎました。
1. Ueber den Tetanusbacillus(破傷風菌について)
『Zeitschrift für Hygiene . Volume 7, pages 225–234』
北里柴三郎 1889年
九州大学医学図書館所蔵 【 詳細情報 】【 本文(詳細画像)】
本論文は、1889年に、ロベルト・コッホの衛生研究所(ベルリン)に在籍していた際に発表した破傷風菌の純粋培養と毒素の性質に関する先駆的研究です。
当時は安定した嫌気培養法が確立されておらず、病原性の解明も不十分でしたが、北里はこれを克服し、毒素こそが発症の主因であることを実証しました。
この成果は感染症学と免疫学の発展に大きく貢献し、後の破傷風血清療法の開発につながりました。
2. Die Pest in Japan(日本におけるペスト)
『Zeitschrift für Hygiene und Infektionskrankheiten. Volume 64 : p. 279-284』
北里柴三郎 1909年
九州大学医学図書館所蔵 【 詳細情報 】【 本文(詳細画像)】
本論文では、19世紀末から日本で発生したペスト流行に対する疫学調査や検疫、ネズミ駆除などの防疫対策が詳述されています。
ペスト菌の性質や感染経路を科学的に分析し、公衆衛生の視点から実効的な防疫体制の構築を論じました。
発表先の『Zeitschrift für Hygiene und Infektionskrankheiten』は結核菌の発見で知られる細菌学の父ロベルト・コッホが創刊した著名誌であり、北里はこの場を通じて日本の衛生対策の成果を国際的に紹介しました。
3. 赤痢病原研究報告 第一(せきりびょうげんけんきゅうほうこく だいいち)
『細菌学雑誌. 25号 : p. 787-810』
志賀潔 1897年(明治30年)
九州大学医学図書館所蔵 【 詳細情報 】【 本文(詳細画像)】
1897年、東京で激しい赤痢の大流行が発生した際、志賀は北里柴三郎が所長を務める伝染病研究所の若手研究者として調査にあたり、患者の便から新しい細菌を分離・培養することに成功しました。
この論文では、その病原体が赤痢の原因であることを実験的に証明し、「赤痢菌(のちの志賀赤痢菌/Shigella dysenteriae type 1)」として世界に報告しています。
北里柴三郎と志賀潔
北里柴三郎と志賀潔は、師弟の関係にありながら、それぞれ独自の功績を残し、日本の感染症対策と細菌学研究の発展に大きな影響を与えました。Submitted:
| Updated:
| Total Views: 406


